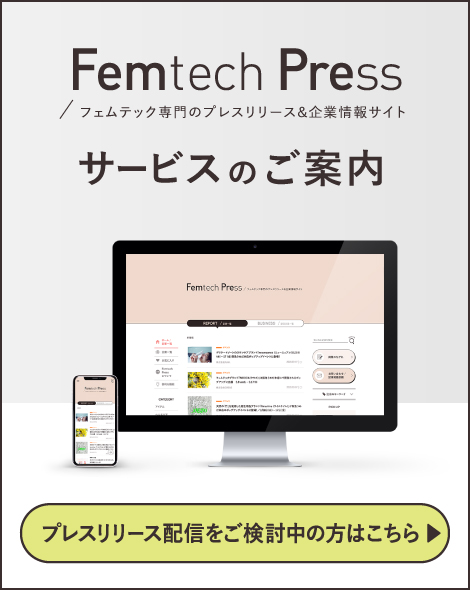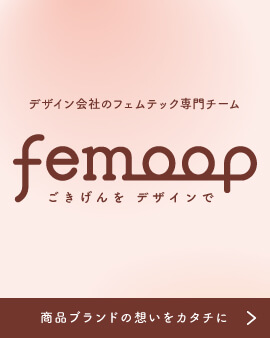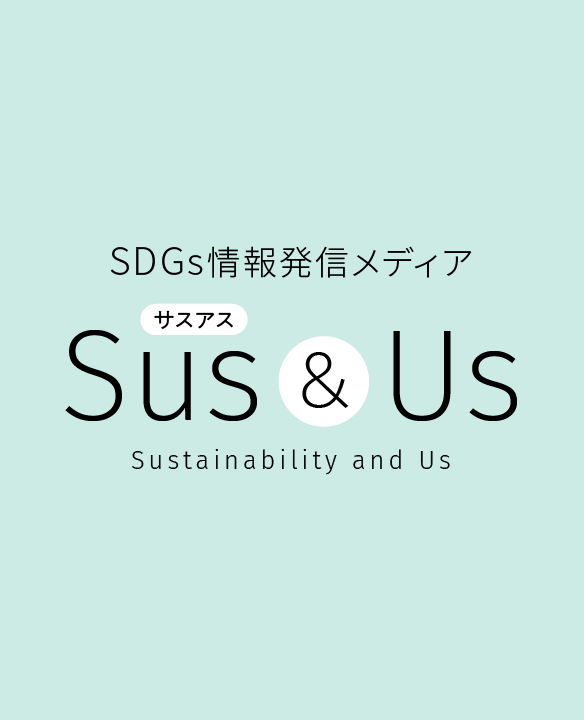特集
全文掲載記事
【特集インタビュー 小林製薬株式会社様】女性のQOLを守る防災へ。デリケートゾーンケアから考える、企業・自治体ができる「フェムケア備蓄」<01>
フェムテックプレス編集部
2025.09.16 17:44
ビジネスにアイデアをひとさじプラス——。
「フェムテックプレス」では、掲載プレスリリースをきっかけに、業界の注目キーワードを深掘り。企業担当者へのインタビューを通して、フェムテック・フェムケアの現場を紐解いていきます。
Vol.17のキーワードは「フェムケア視点の防災対策」。
災害時の「おりものシート」備蓄率が、わずか7.9%※1 ——この数字、ご存じですか?
東日本大震災以降、女性の防災意識は高まったものの、避難所では依然としてデリケートゾーンケアの備えが不十分です。
内閣府男女共同参画局が示す防災・復興ガイドラインの「備蓄チェックシート」※2におりものシートについても記載されていますが、その必要性に対しては、まだ理解が十分とは言えません。
そこで9月の防災月間、フェムテックプレスは、日本初のおりものシート「サラサーティ」を開発し、30年以上女性に寄り添ってきた小林製薬株式会社にインタビューを実施しました。
おりものシートの役割、防災時のメリット、そして製品に込めた想いを通して、女性のQOLを守る「デリケートゾーンケア」の重要性、そして企業・自治体が見直すべき「防災備蓄の新常識」を、深く探ります。
※1 地方公共団体における男女共同参画の視点からの防災・復興に係る取組状況についてフォローアップ調査結果(令和6年6月内閣府実施 P19掲載)
https://www.gender.go.jp/policy/saigai/fukkou/pdf/chousa/r5_zentaigauyou.pdf
※2災害対応力を強化する女性の視点災害対応力を強化する女性の視点~男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン~(令和2年5月 内閣府男女共同参画局)
https://www.gender.go.jp/policy/saigai/fukkou/pdf/guidelene_01.pdf
https://www.gender.go.jp/policy/saigai/fukkou/pdf/guidelene_06.pdf

【Profile】
小林製薬株式会社
(左から)広報担当 黒岩さん 古川さん
フェムケアプロジェクト 白石さん
サラサーティ ブランドマネージャー 山下さん
【INDEX】
01 “声なき声”に耳を澄まし、“あったらいいな”をカタチに。小林製薬が大切にしてきたもの。
02 正しく知ることが、最初のケアになる。成長のサインである「おりもの」を、親子や学校でどう伝える?
03 “自分のからだ”に合った備えが、いちばんの安心になる。小林製薬と考える「フェムケア視点の災害時のセルフケア」。
04 女性の人生に、もっと寄り添うために。ブランドの垣根を超えて生まれた「フェムケアプロジェクト」。
【01】“声なき声”に耳を澄まし、“あったらいいな”をカタチに。
小林製薬が大切にしてきたもの。
—— 御社の事業概要についてお聞かせください。
黒岩さん:
小林製薬では、「見過ごされがちなお困りごとを解決し、人々の可能性を支援する」というパーパスを掲げ、事業を展開しています。
これは、一人ひとりの暮らしの中にある、普段は気づかれにくいお困りごとに目を向け、世の中にまだないアイデアや技術で、お客様の快適で健康的な暮らしを支え、社会での活躍を後押ししたい——そんな想いが込められています。

特徴の一つに、お客様ご自身もまだ気づいていないような“潜在的ニーズ”を見つけ、製品というカタチで開発・提案し、新しい習慣や市場を生み出してきたことが挙げられます。
例えば「熱さまシート」は、当時は薬や濡れタオル、アイスまくらが主な対応手段でしたが、「ズレにくく、長時間冷やせるものがあれば助かる」というお声に応え、額に貼る冷却製品として開発・発売しました。
また、そうした新しい商品を世の中に届けていくためには、「一目で用途が分かるネーミング」や「使い方が伝わるパッケージ」も欠かせません。私たちは、お客様に手に取っていただけるよう、わかりやすい商品設計にもこだわりを持っています。

—— 日本初のおりものシート「サラサーティ」は、どのように誕生したのでしょうか。
山下さん:
今では定番となっているおりものシートですが、当時は“おりもの”という言葉自体がタブー視されており、多くの女性がひそかに対処しているものでした。
私たちは、そうした部分にこそ悩みやニーズがあるのではないかと独自調査を実施し、約8割の女性が、おりものによる下着の汚れや不快感に悩んでいるという実態を明らかにしました。
にもかかわらず、当時の対処法は、生理用ナプキンの代用やティッシュの使用、頻繁な下着の交換など、不便で負担の大きいものばかりでした。
また、開発のきっかけの一つには、当時の海外視察で、海外ではおりものシートが一般的に使われていたにもかかわらず、日本にはまだ存在しないことに疑問を持った、という背景もあります。
そこで私たちは、「女性による、女性のためのおりもの対策製品」を作ろうと、開発をスタートさせました。とはいえ、当時は情報も専門家も少なく、「おりものとは?」「量は?」「ニオイの原因は?」と、まさに初めて尽くしの研究・調査の連続でした。
手作りのシートによる回収・測定から、ニオイの原因物質“酪酸”の特定、肌にやさしい薄さや装着感の追求まで、数々の試行錯誤を経て、厚さ約2ミリの日本初のおりものシート「サラサーティ」が誕生しました。
「サラサーティ」というネーミングには、「さらさらが30日(サーティ)続くように」という想いが込められています。
—— 「おりものシート」という新習慣を提案するにあたり、当時の社内や世の中の反応はいかがでしたか。また、1988年発売から現在までで、ニーズに変化はありましたか。

山下さん:
発売当初の調査では、「自分だけだと思っていたけれど、みんな同じように悩んでいたと知って安心した」という声が多く寄せられました。
それまでは「自分のからだに何か異常があるのでは?」と不安を抱えていた方が多かったのです。
そこで私たちは、「おりものは健康な女性が経験している、ごく自然なこと」だという正しい知識を伝え、少しでも心が軽くなるようにと、テレビCMの制作を決めました。
あえて「おりものシート」という名称を前面に出し、その言葉を伝えてくださる女優さんを探すのにも、大変な苦労があったと聞いています。
そうして生まれた「サラサーティ」は、発売からわずか11ヵ月で200万人のご愛用者を超える大ヒットとなりました。
一方で、「おりもの」という言葉をCMで聞くことに抵抗を感じた方から、お客様相談室に多数のお声をいただいたという側面もあります。

白石さん:
初代のCMは、女優さんのアップから始まり、「おりもので悩んでいるのは、あなただけだと思っていませんか。」という問いかけからスタートし、続けて「実は、女性の約8割がおりもので悩んでいます」というデータを紹介する構成でした。
そのメッセージは、これまで誰にも言えず、一人で抱えていた方々の心に響いたのだと思います。
発売当時にいただいたお客様の声には、「自分のことを代弁してくれた」「ようやく口にしてもいいんだと思えた」など、共感の言葉が数多く寄せられました。
なかには、「おりものが気になって白いパンツがはけなかったけれど、おりものシートがあることで好きな服を自由に着られるようになった」というお声もありました。
また、「“下着を洗うのは女性のたしなみ”だと言われてきましたが、おりものシートを使い始めてからは、そのストレスから解放されました」という声も届いています。
こうした努力や我慢を、少しでも軽くし、女性たちを解放することができたのではないかと感じています。
山下さん:
現在は「フェムケア」「フェムテック」という言葉が浸透し、生理についてもオープンに話せる機会が増えてきましたが、おりものに関しては、まだまだ人と話すきっかけが少ないのが現状です。
だからこそ私たちは、イベントや啓発活動を通じて、おりものの役割や、おりものシートの健康面でのメリットを発信し、少しでも多くの方に、「話していいことなんだ」と思っていただけるよう、これからも活動を続けていきます。
この記事の企業をCHECK!
関連記事
-

アイテム
デリケートな肌を守りながら、狭いI・Oゾーンもラクに剃れる! VIOゾーン専用設計カミソリ「ピアニィVIO そる用」 フェザー安全剃刀から2026年2月新発売
フェザー安全剃刀株式会社
2026.02.06
-

特集
全文掲載記事
【合同会社すずはな インタビュー】インナーパフュームとは?韓国発「COME INSIDE ME」が提案する“自分だけに香る”フェムケア習慣
合同会社すずはな
2026.01.28
-

アイテム
全文掲載記事
「香りでととのい、色でときめく」フェムケアブランド『YURiiRO』がリニューアル!神田うのも登壇
株式会社E-seeds
2026.01.22
-

アイテム
累計出荷数261万本*¹突破の人気デリケートゾーン専用泡ソープから数量限定で、豊潤で華やかなiroha INTIMATE WASH 【 FOAM TYPE 】「ローズブルームの香り」が新登場!
株式会社TENGA
2026.01.06
-

経営情報
新たな検査手法の可能性を「日本性感染症学会」で発表。『おりものシート』活用で自宅検査の実用化へ
株式会社LDHD
2025.12.26